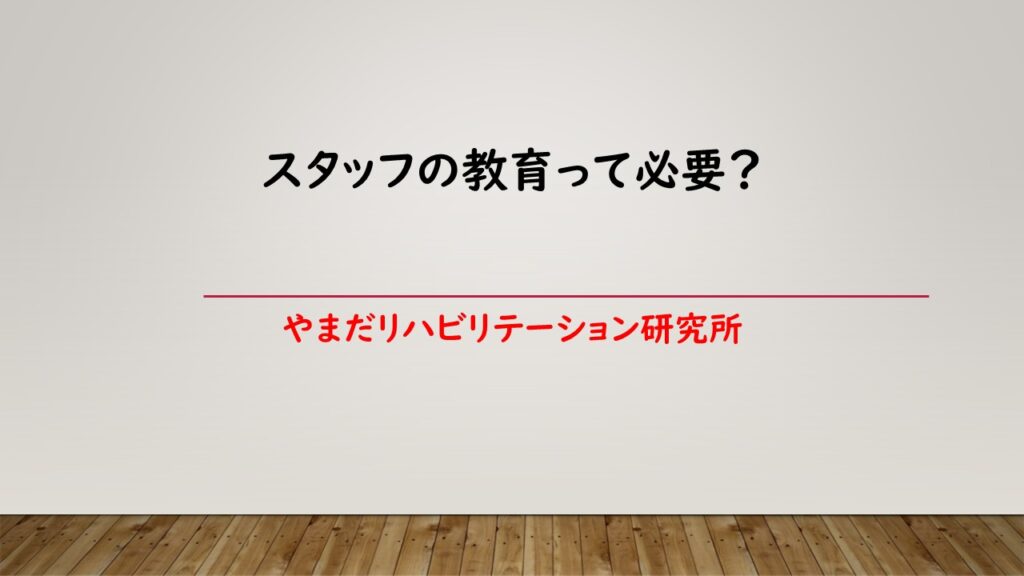
訪問看護ステーションとか児童デイで働くリハビリスタッフや看護師さんの教育って必要なんでしょうか?
私は必要だと考えているので、サポート事業を行っています。
私の場合は、個人のセラピストさんに直接塾みたいな感じで何かをレクチャーするのではなくて、事業所としての教育にかかわっていきたいと考えているので、できる事なら、事業所の経営者さんとか管理者さんクラスの方に教育の必要性に気づいてもらえたらいいなと思い日々いろいろと発信しています。
生活を考えるという視点
これまで病院という場所で働いてきた理学療法士さんや作業療法士さんにとって、地域とか生活期などの領域といわれるような訪問看護ステーション、児童発達支援や放課後等デイサービス、介護保険でのデイサービスなどの事業所でのリハビリテーションっていうのは、けっして病院で提供していたリハと同じものを提供すればよいというわけではないと考えています。
しかしながら、制度のことや事業所のルール的なものをレクチャーすることのできる事業所はありますが、生活期でのリハビリテーションの在り方や、生活を見るリハビリテーションの進め方のレクチャーをする事業所は少ないのかなと感じています。
セラピスト自身の自己研鑽に任せている事業所も多いのではないでしょうか?
セラピスト任せにするのではなくて、事業所としてどのようなリハビリテーションを対象者に提供するのかということをきちんと考えていくことが必要だと思います
- 「生活を見る」という視点
- 「セラピストが関わらない時間の生活を考える」視点
といったものをしっかりと理解してリハビリテーションを展開することが必要なのかなと考えています。
制度や時代の変化にマッチしたリハビリテーション
オンライン講義の資料をいろいろ公開していますが、講義の中では厚労省の資料の紹介なども行っています。
◆2025年9月時点でダウンロードできる講義資料一覧
講義などでいろいろ厚労省の資料をもとにお話をするのですが、公開されている資料についてきちんと知っているセラピストさんはものすごく少数派です。
正直に書くと制度の変化や時代の流れにマッチしているとは言い難いリハビリテーションを実践されている事業所さんも少ないなと感じています。
だからこそ事業所としてしっかりとしたリハビリテーションの方針や指針を決定して、それに沿ったリハビリテーションを展開することが必要。
セラピストここの考え方に任せたバラバラなリハビリテーションの提供ではなく、事業所の考え方に沿ったリハビリテーションの提供が必要な時代になってきていると考えています。
必要な時期に、適切な目標を設定して、必要な期間・頻度でリハビリテーションを提供すること
これが現在の生活期における訪問看護リハ、訪問リハの基本的な考え方です。
事業所でのリハビリテーションの提供の在り方で悩んでおられる経営者さんや管理者さんがおられましたらいつでもサポートさせていただきますので、ご相談ください。
◆サポート概要
◆サポートのことあれこれ(コラム)
お問い合わせはお気軽にね、Zoomなどでお話ししながら打合せさせていただきます。
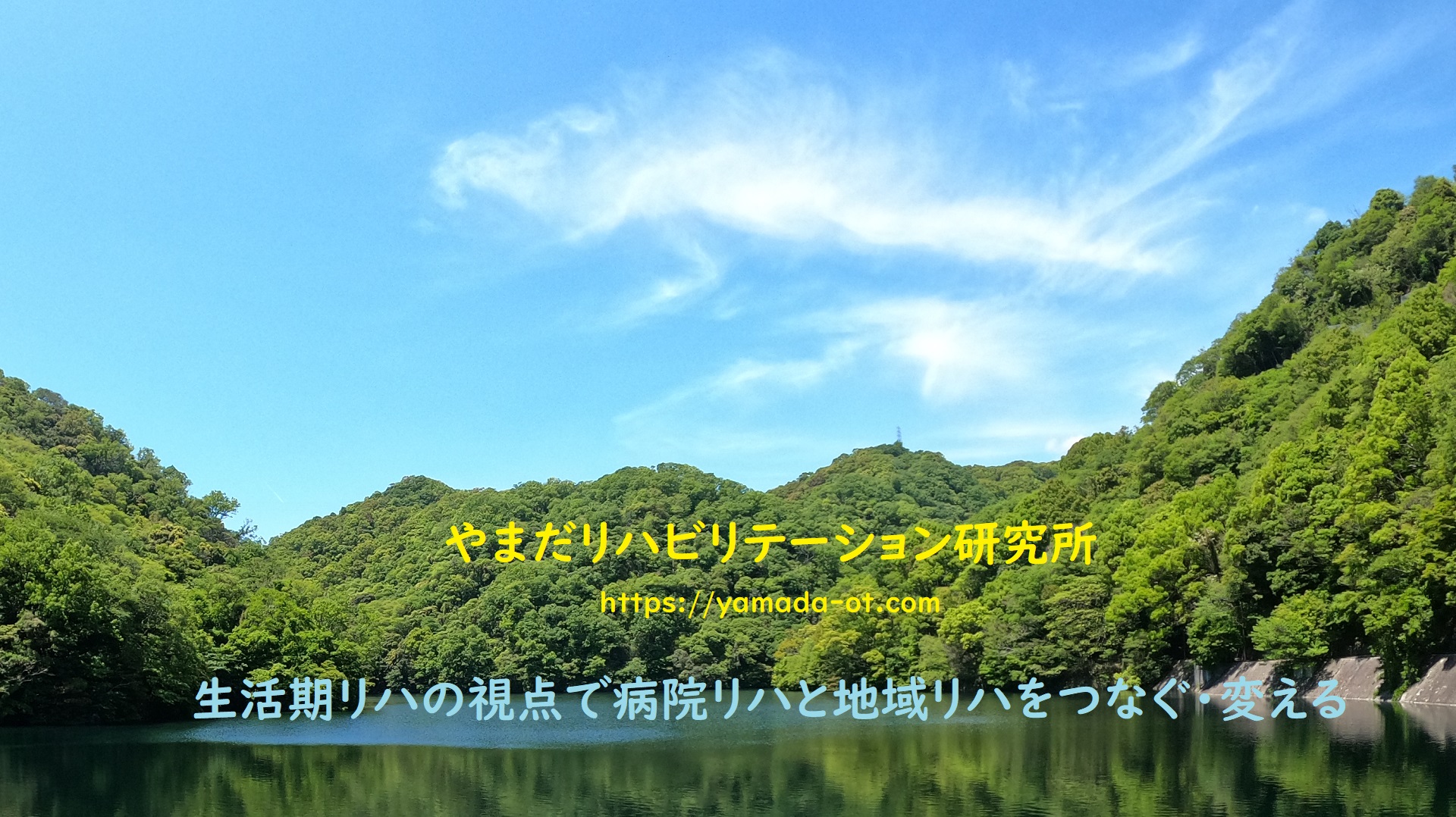
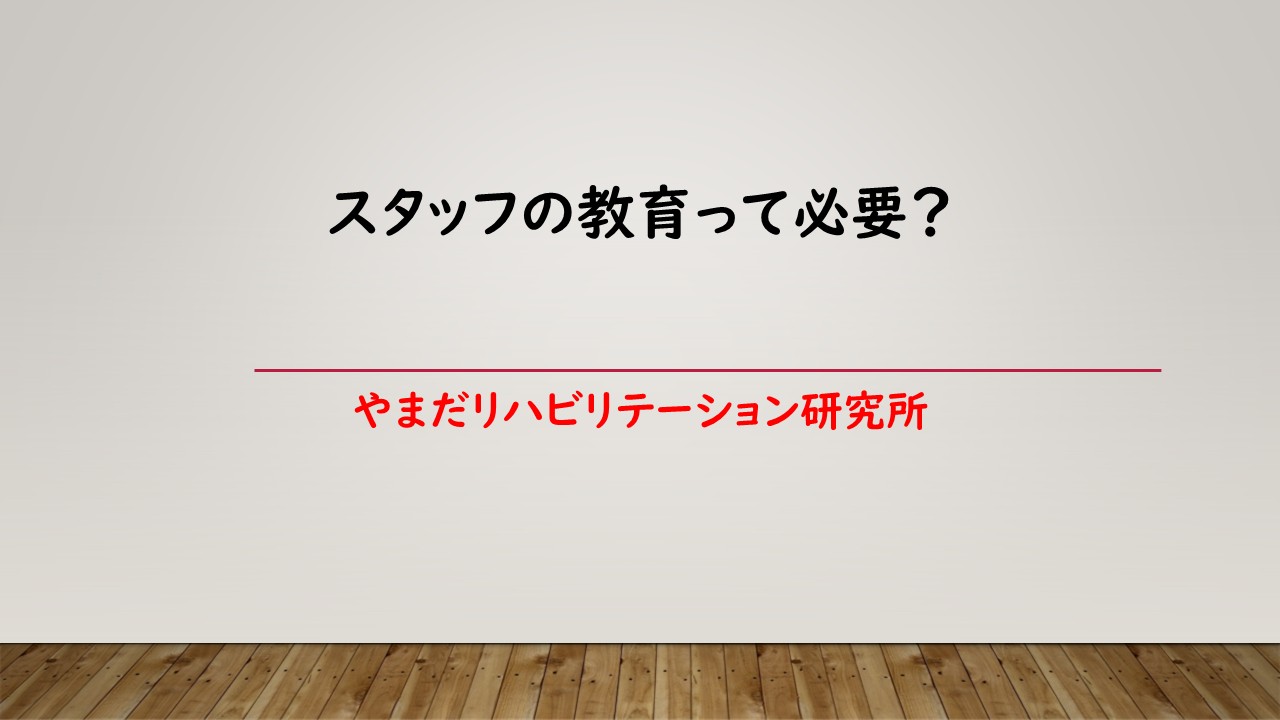


コメント