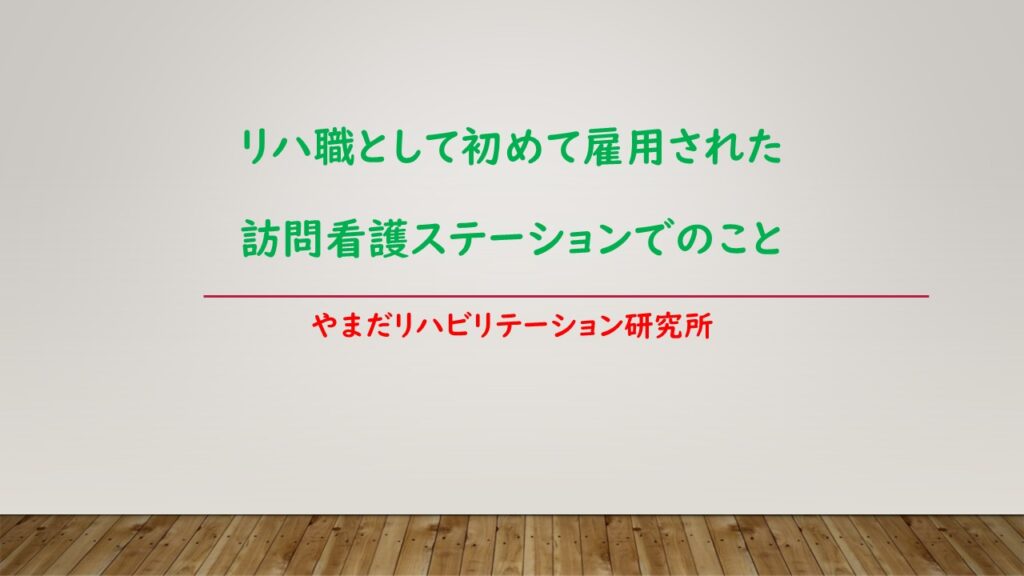
病院や老健の勤務を経て初めて訪問看護ステーションに勤務したのは30代半ばの時でした。週4勤務で常勤という職場でした。もう一日の仕事をどうしようかなと思っていたところ、とある研修会で講義をしてのちの懇親会でエリアも経営者も全く異なる訪問看護ステーションの管理者さんから、「リハ職がいないのですが非常勤でもいいからうちで勤務しませんか?」と声をかけていただきました。
週4の訪問看護はのちに退職しましたが、リハ中心で看護師さんが少数の事業所でした。その事業所でいろいろ思うこともあったので、看護師さんしかいない訪問看護ステーションという、訪問看護の王道みたいなところでの勤務は私にとっては大変。ありがたいお話でしたので即決で勤務することになりました。のちに、別の訪問看護ステーションの管理者さんからもお声をかけていただき、その事業所初のセラピストとして勤務することになりました。
ですので、訪問看護ステーションで初めて雇用するセラピストとして働いた経験は計2か所となります。
看護師さんが5人くらいのステーション。管理者さんもバンバン訪問に行っています。福祉用品のレンタルと訪問介護、居宅介護も併設されています。
そんな事業所に週1勤務を開始。
大阪市内の事業所でしたので、自転車で平均6~7件ほど私は担当していました。
この事業所で管理者さんから言われたことは、
「リハのみの依頼のケースはすべて断るか、他の事業所を紹介します。看護と併用するケースをやまださんには担当してもらいます。」
という言葉でした。それまでに勤務していたリハ多数の訪問看護とは全く反対の方針でした。でも私としてはそれこそが訪問看護ステーションのリハビリテーションというものだろうと納得したものです。
これね、最近の話ではなくて30代のころのことなので、実は20年以上前の話ですよ。そんなときから、リハと看護の在り方をきちんと考えておられた管理者さんでした。
リハ多数の訪問看護ステーションでは、私の担当ケースの担当期間は長くなりますが、このA訪問看護ステーションでは当時からガンの利用者さんや難病の重度のケースなどにも対応していたこともあり、私の担当ケースの平均担当期間は1年未満でした。とにかく回転が速い、新規がどんどん来ていました。
そんな中で、看護師の介入が必須な重度のケースを担当することが多くなり、必然的にリハと看護の連携がないと対応できないことが多く、そのことが訪問看護ステーションにおける「リハと看護の連携の必要性」を私がしっかり伝えていきたいなと考えるようになったきっかけでもあります。
じゃあ、この事業所でのお仕事がすべて順調だったのかというとそうでもありません。
もともと看護師さんのみが担当していたケースに、私が途中から関わるようになったことがありました。点滴を中心に3か月ほど看護師さんが介入していたケース。
3か月前は歩いていた、今は寝たきり。点滴開始してから徐々に運動機能が悪化してきた。
私としては、「もっと早くから作業療法士として私が関わっていたら、ここまで運動機能が悪化しなくて済んだんじゃないか?」というのが初回訪問で感じたことです。
初回訪問を終えた私は、率直に管理者にそのことを伝えました。管理者さんも反省しきりでした。ここまで急激に悪化するとは想定していなかったようです。
このことがきっかけで、私もいろいろ反省し、自分が担当ではないケースについてもいろいろ情報を収集すべきというか、看護師さんのみが担当しているケースであっても関心を持っておくことが必要だと気付きました。まあもちろんすべてのケースを把握することはかなり難しいので、
- 新規のケースの情報はチェックする
- 申し送りとか昼休みとかに看護師さんが話題にしているケースの話は一緒に聞いておく
- 24時間対応でよく名前が挙がるケースの情報はちょっと見ておく
- 看護師さんにリハのことをちょこちょこ伝える
- 時間があるときは看護師さんの訪問に同行する
可能な範囲でこのようなことをするようになっていきました。リハ少数の訪問看護ステーションでの作業療法士としての機能を最大限に発揮するための行動指針でした。
ここでの勤務の経験が、訪問看護ステーションで多職種連携をスムースに行うためにはどう行動すべきかということの基本となっています。
興味ある方こちらの資料もご覧ください。
◆2025年9月時点でダウンロードできる講義資料一覧
お問い合わせなど
ブログやSNSまとめ
- ブログ
このサイトです
やまだリハビリテーションらぼ - noteサイト
もう一つのブログサイトです
やまだリハビリテーション研究所のnote - Facebookページ
やまだリハビリテーション研究所Facebookページ - X(旧Twitter)
https://twitter.com/yamada_ot_labo - インスタグラム
https://www.instagram.com/yamada_ot_labo/?hl=ja - YouTube @yamada-ot-labo
やまだリハビリテーション研究所のYouTubeのチャンネル - やまだリハビリテーション研究所公式LINEアカウント

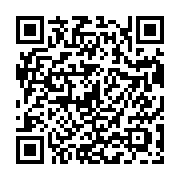
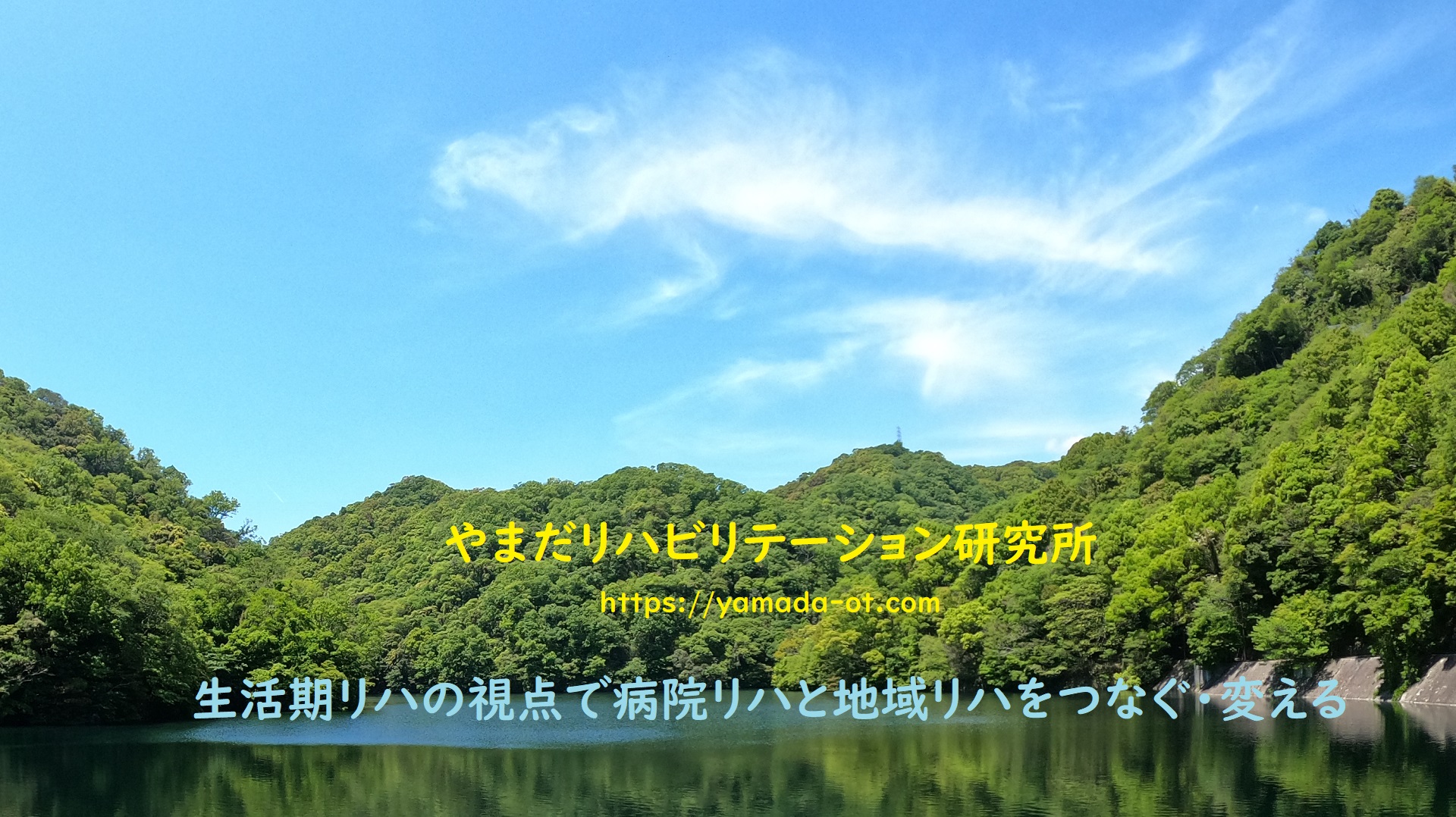
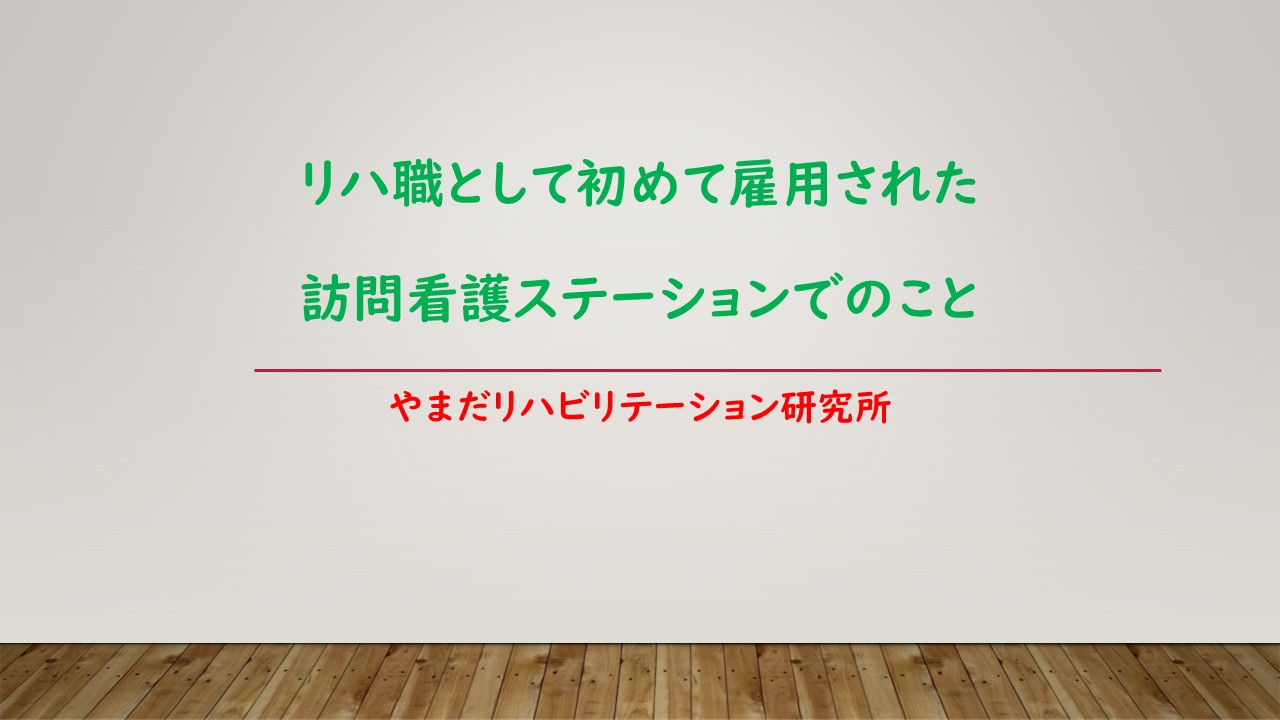


コメント